どうもボスやんです。
私は夜だけパパ見知りになる息子をなんとか克服したい!という思いから、様々な方法をトライして夜だけパパ見知りの対処法を模索していました。
今回は成果のあったパパ見知り対策を記事としてまとめてみましたので、夜だけパパ見知りで悩まされているパパさんがいましたら、私が実践した方法も是非トライしてみて下さい。
この夜だけパパ見知りの対策法は、夜パパが一人で寝かしつけを行う時に有効な方法になります。
パパ見知りについては以前にも他の記事でまとめています。
・夜だけパパ見知りって何?
・この夜だけパパ見知りっていつから始まるの?
・何で夜だけパパ見知りが起こるの?
・こうなった時の対処法はないの?
上記のようにそもそもパパ見知りとはなんぞや、ということから解説していますので、気になる方は下記記事も参考にして見てください。
これから説明する対処法は、この時の対処法から更にグレードアップしています!
私が実践した夜だけパパ見知り対策方法!
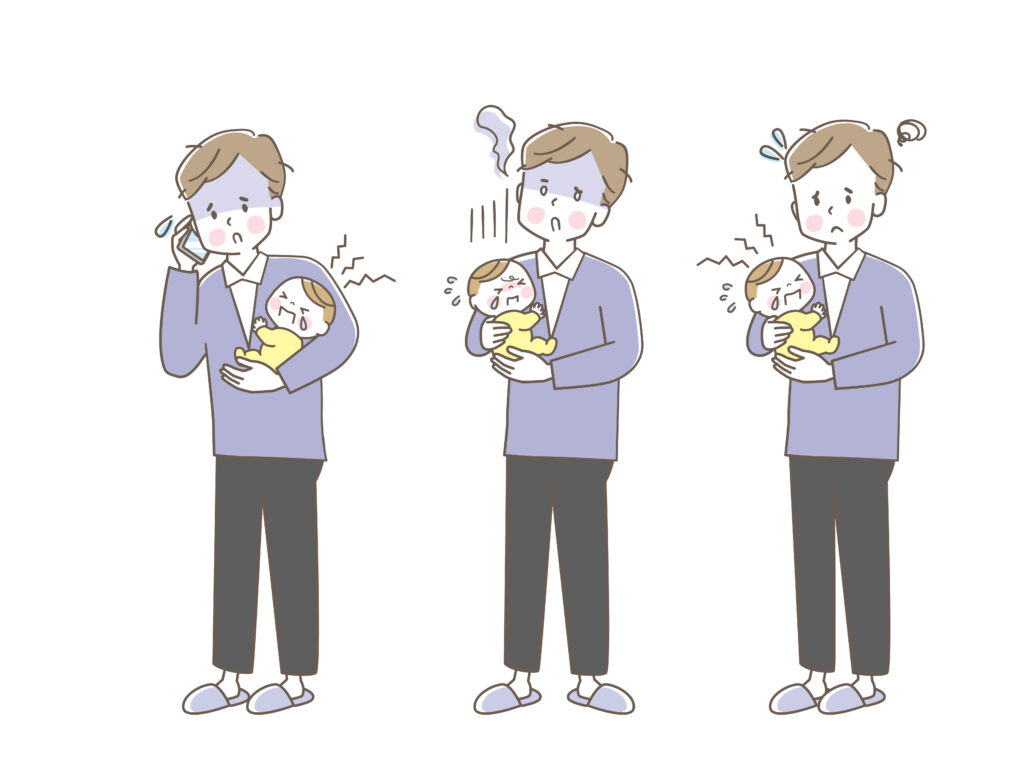
なぜか夜だけパパ見知りになり、パパの抱っこでは全く泣き止んでくれない我が子。
夜の寝かしつけ、どうしてもパパ一人で寝かしつけができない。。。
もしかすると、この記事を読む前に色々と試行錯誤されたパパさんもいるのではないでしょうか。
このパパ見知りは一筋縄ではいかないのが現実ですよね。。。
私もいっぱい悩みました。
そして沢山試行錯誤を重ねることで、夜だけパパ見知りをある程度抑え込む方法を見つけ出すことができました。
ここである程度抑え込む方法と記載したのは、子供の状態によっては100%パパ見知りを抑え込むことができないからです。(この対策法が全く通用しない時もありました)
それでも私はこの方法で我が子のパパ見知りを高確率で抑えることができていますので、皆様も是非トライして見てください。
この対策には順序がありますので、それぞれ順を追って説明していきます。
対策その①パパの体温を下げる
我が子を寝かしつける際、パパの体温が高いと抱っこした時に直ぐグズる(泣き出す)ことが多かったです。
実際に赤ちゃんは体温調整機能がまだまだ未発達なため、暑さを感じやすいところがあるみたいです。
なので、パパの体温が熱いとそれが直に子供に伝わってしまい、その熱さが不快となって泣き出してしまう可能性が考えられます。
私は息子をお風呂に入れた後、その流れで私もお風呂に入り、お風呂から上がった後はそのまま息子の寝かしつけを行っていたのでお風呂上がりの熱がそのまま息子に伝わってしまい泣き出す・・・ということが多々ありました。
それで『もしかすると私の体温が高いために子供が不快になっているのでは?』と気づくようになりました。
なので、まずは寝かしつけの前段階として自分の体温を平常時に下げるようにしましょう。
対策その②片手抱っこ&片手ミルク

ここからが少しテクニックが必要になってきます。
子供を寝かしつける前に、事前に電気のリモコンを床に置いておいて下さい。
なぜ床なの?と思うかもしれませんが、その理由は後ほど説明します。
まず我が家はミルクを与えながら寝かしつけ作業に入ります。
この際、立った状態で我が子を片手で抱っこし、もう一方の手でミルクを与えます。
赤ちゃんは立った状態であやした方が泣き止む性質がありますので、立って子供をあやすことが重要です。
なぜそのような性質があるのかは下記記事にまとめていますので、気になる方はこちらもチェックしてみて下さい。
立った状態でゆらゆら身体を動かすのもポイントですね。
この状態を維持したまま子供をあやし、ある程度ミルクが減ったら(約半分くらい)どちらかの足で電気のリモコンの消灯ボタンを押します。(アレクサ機能があればわざわざこの作業をしなくても良いかもしれません。笑)
電気を消灯することで子供に『もう寝る時間なんだ』と学習してもらう必要があります。
この状態で子供がミルクを飲み終えるor眠りだすまであやし続けて下さい。
これでも泣き止まない場合の最終手段として、ホワイトノイズを使用するも良いかもしれません。
うちの息子は生後半年が経った今でもドライヤーの音が効果的です。
ドライヤーの音を聞かすと大人しくなるので、その隙を見てミルクを与えて寝かしつけを行う時もあります。
対処その③10分以上抱っこ⇨布団に着地
対処その②で子供はウトウトしているか、もう腕の中で寝ているかもしれません。
ここまでくれば、あとは然程難しくはありません。
後は10分~15分程度立ったまま抱っこし続け、ゆっくり赤ちゃんを布団やベビーベッドに降ろすだけです。
私はこの対処①~③を行うことで、パパ一人で寝かしつけを行うことができるようになりました。
途中泣き出す場合もありますが、その際は抱っこの仕方を縦抱きに変えたり、歩きながら抱っこしたりと、その時に子供が落ち着く抱っこの方法を模索するようにして下さい。(何しても泣き止まない時もありますので、その時は無心であやすようにして下さい。笑)
番外編
実はこの番外編が割りと大切になってくるのではないかと思います。
パパの皆様は平日は仕事のため、子供と接する時間は妻に比べると圧倒的に少ないですよね。
この子供接している時間に比例して子供がパパ見知りになる頻度も少なくなっていきます。
なので、せめて休日くらいは妻よりも多く子供のお世話を率先してやるべきだと私は考えています。
休日も妻と一緒に子供のお世話をしているだけでは、パパ見知りは克服されないと思います。
休日は子供と遊ぶパパさんも多いと思いますが、それでは単純に『遊んでくれる人』としか認識されないのだと思います。
パパ見知りを克服するためには子供に『お世話もしてくれる人』と認識してもらうことも大切だと思いますので、休日は率先して子供のお世話を行ってみて下さい。
私は休日率先して息子のお世話をするようになってから、息子の感じが少し変わった気がしています。(抱っこ中、息子が私をずっと見つめるようになりました)
実はこれがパパ見知りを克服するのに一番大切な方法かもしれませんので、こちらも是非トライしてみて下さい。
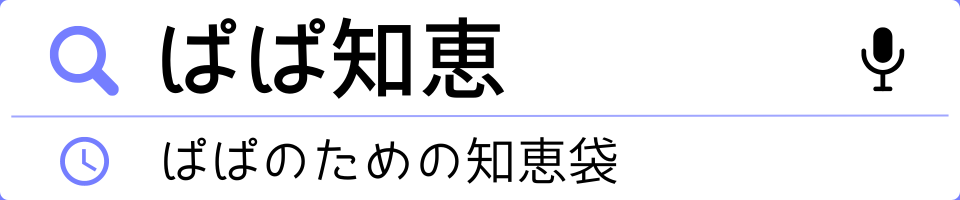
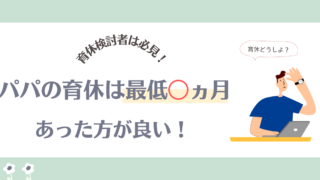
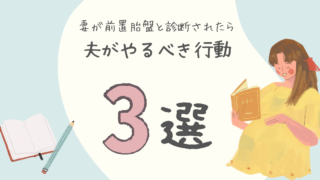


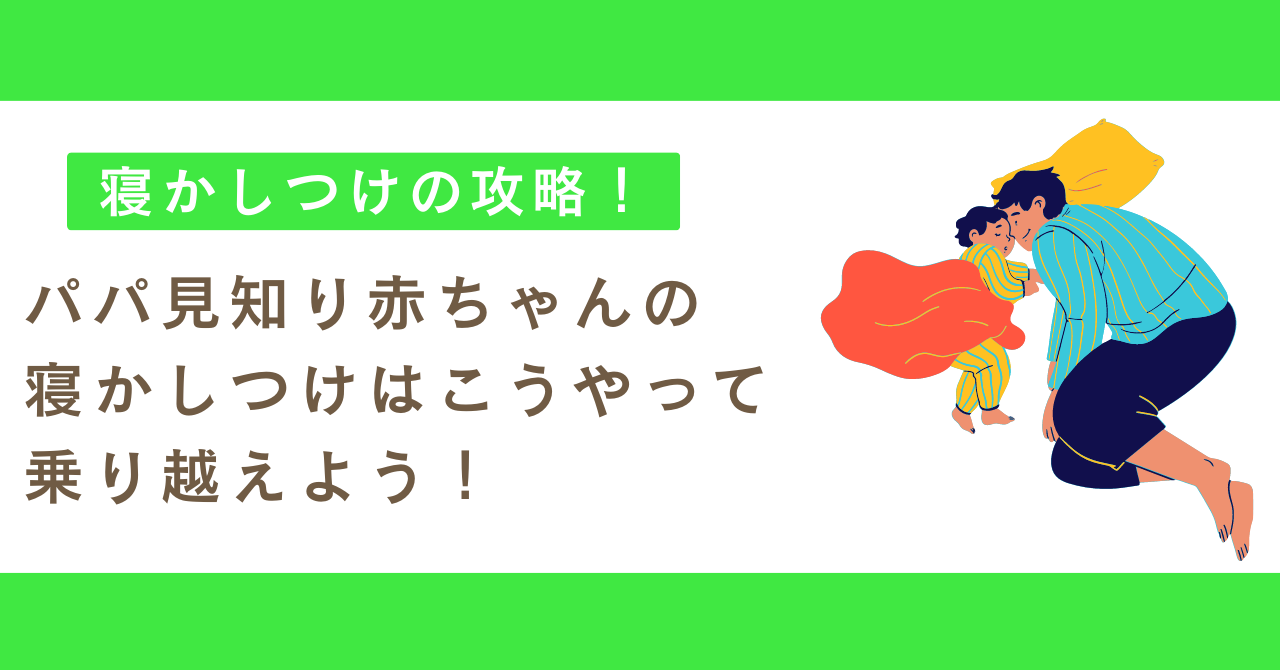
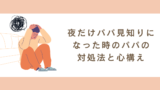
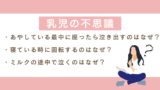


コメント